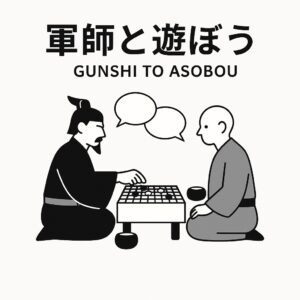この本、読みました! 第0回 親子読書のはじまり
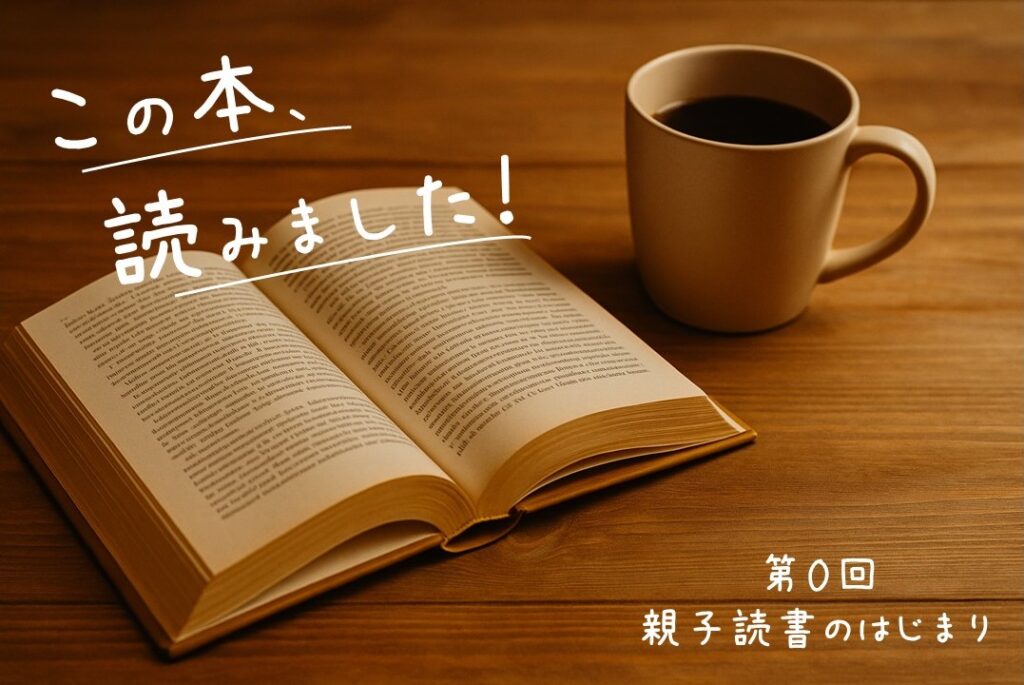
1. はじめに
我が家には、ジャンルは違えど本を読むのが好きな人と、そうでない人がいます。
妻は幼いころからの読書家で、今も幅広いジャンルの本を楽しむタイプ。
一方の私はというと、読書といえば投資や実用書ばかりで、小説にはあまり手を伸ばしてきませんでした。
そんな家庭なので、息子に自然な読書習慣が根づくかどうかは未知数でした。
それでも、幼いころは絵本の読み聞かせから始まり、小学校に入ってからも妻が児童書を薦めてくれました。
しかし、成長するにつれて息子の興味はYouTubeなどの動画へ。気づけば、本を手に取る時間は減っていきました。
それでも、「完全に本から離れてしまったわけではない」というのが救いでした。
学校の「読書週間」には図書室から本を借りてきては、科学系や学習漫画を楽しんでいました。
小説に関しては、星新一さんの作品を時折読む程度。無理に薦めたり、強制はしないのが我が家の方針でした。
2. 眠っていた芽
中学受験勉強を始めたころ、社会が苦手だった息子に「まんが日本の歴史」を薦めたことがあります。
もともと4年生のころから家に全巻そろっていたのに、ずっと手つかずだったシリーズです。
試しに読み始めると意外にも夢中になり、歴史の流れをつかむ助けにもなりました。
この時点でも、まだ「本格的な読書習慣」とは呼べない段階でしたが、
少なくとも「本を読むことは悪くない」という感覚は残っていたのだと思います。
3. きっかけはテスト問題
転機は2025年6月の浜学園公開学力テストでした。
試験問題に出てきた小説が、私の心をつかんだのです。
解答用紙を見ながら「これは本編を読まねば」と決意し、書店へ直行。
その作品――『成瀬は天下を取りにいく』――を読み終えたとき、
私は「若さって素晴らしい」と心が震えるような感動を覚えました。
これが、後に「親子で同じ本を読む」という習慣へつながっていきます。
とはいえ、この時はまだ自分たちの間にそんな未来が待っているとは思ってもみませんでした。
4. 親子で同じ本を読むということ
親子で同じ本を読むのは、簡単そうでなかなか難しいものです。
私が小学生向けの本を手に取る機会など想像もしなかったし、
息子が私の好きなマネー本や歴史小説を読む姿も想像できませんでした。
けれど、中学入試で扱われる小説に触れる中で、その完成度とテーマの深さに驚きました。
「これは大人が読んでも損はない」と思える作品が次々と現れたのです。
そして、読後に交わすわずかな感想や会話が、想像以上に楽しいことにも気づきました。
5. これから
こうして始まった親子読書は、まだ日が浅いものの、確かな手応えがあります。
この連載では、私たちが実際に読んだ本と、そのときの親子のやりとりや気づきを記録していきます。
第1回は、親子読書の扉を開いてくれた『成瀬は天下を取りにいく』です。
次回からの数回は、以下の作品を取り上げます。
- 第1回 成瀬は天下を取りにいく(宮島未奈)
- 第2回 きみの話を聞かせてくれよ(村上雅郁)
- 第3回 あと少し、もう少し(瀬尾まいこ)
この本たちが、親子の間にどんな会話を生み、どんな景色を見せてくれたのか――ぜひお付き合いください。
6. タイトルについて
この企画名は、女優・鈴木保奈美さんが出演されているテレビ番組
『あの本、読みました?』から着想を得ました。
目指すのは、あの番組のように“本を通じた人のつながり”を温かく描くこと。
将来、家族でこの記録を読み返して、「あの頃はこんなふうに本を読んでいたんだね」と笑い合える日が来れば、これほど幸せなことはありません。