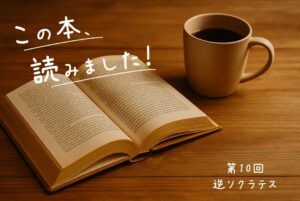50歳からの住宅ローンと投資――「規律」が導くフルローン戦略の合理性
第1回では、リバランスをためらう心理と「感情より規律」の重要性を。
第2回では、住宅購入とリバランスの関係を。
そして今回は、いよいよシリーズ完結編。
テーマは「50歳からの住宅ローン」と「投資の継続」。
年収1,000万円、金融資産6,500万円の相談者が、
“定年までの10年間をどう生きるか”を真剣に問います。
前提条件
年収1,000万円(税引前)/50歳
定年は60歳で退職金1,500万円を受け取る見込み。
定年後の収入(再雇用・転職)は未定。
リスク資産については引き続き、リターン15.27%・リスク17.27%とします。
🗣️ 相談者
先ほどは自己資金1,000万円を仮定しましたが、
6,500万円の金融資産を持つ私にとって、マンションの頭金をいくらにしてローンを組むのが一番得ですか?
ローンを組むと手元の株を売らなくて済むので、投資は続けたいんです。
💬 MK
承知しました。最適な戦略は、「手元の投資資産を最大限守り、定年後のリスクに備える」ことです。
そのためには、ローンを最大限活用し、自己資金の支出を極限まで減らすのが合理的です。ここで言う「ローンの最大活用」とは、単に“借りられるだけ借りる”ことではありません。
確実に返済できるキャッシュフローの範囲で、現金を温存することを意味します。
この「温存した現金」が、将来の生活防衛や投資継続の余力になります。
🗣️ 相談者
全額ローンに近い形ですか?
でも、50歳で5,000万円も借りて、60歳で定年なのに返せますか?
長生きリスクも心配で、現金を残さないのは怖いですが…。
💬 MK
50歳という年齢こそ、ローン活用が規律ある戦略になります。
確かにローンは負債ですが、あなたのように安定した高収入(年収1,000万円)と確定的な退職金1,500万円を持つ人は、金融機関から見ても「高属性」と呼ばれる層です。
この属性がある人は、借入金利よりも投資の期待リターンのほうが高い可能性があり、
ローンを「リスク分散の一部」として活用することが合理的になります。
【具体的な戦略】
返済期間を15年に設定し、物件価格5,000万円を上限に、借入の最大化を目標にします。
これにより、自己資金の支出は諸費用と合わせて約300万円に抑えられます。
🗣️ 相談者
300万円ですか!手元に6,200万円近く残りますね。
でも、15年ローンだと65歳まで負債が残るのは不安です。
💬 MK
規律的な解決策があります。
あなたは定年時に1,500万円の退職金を受け取ります。
この退職金を、60歳時点のローン残債(約1,800万円)の一括繰上返済に充てることを、最初から規律として決めておくのです。「繰上返済」とは、予定より早くローンを返して利息負担を減らす行為のこと。
これは確実な支出削減、すなわち「確実なリターン」です。
退職金をこの確実なリターンに使うことは、投資以上に合理的な選択です。
【教訓 I】確実な資金で負債リスクをヘッジする
退職金を「繰上返済専用資金」としてあらかじめ確保しておくことで、
ローンは“老後不安の種”ではなく、運用継続を守るクッションになります。
🗣️ 相談者
なるほど!返済期間を15年に設定することで、月々の返済負担を抑えながら、手元資金と投資余力を維持できるのですね。
実質的には10年で完済する計画、ということですね。
でも、5,000万円も借りられるものですか?
💬 MK
あなたの年収と定年までの期間から見ても、4,000万円超の借入は安全圏です。
一般的に、住宅ローンの限度額は年収の5〜7倍と言われています。また、年収1,000万円の方であれば、年間返済額が年収の35%以下であれば借入可能とされています。
計算すると、
年収1,000万円 × 35% × 15年 = 5,250万円 > 5,000万円。
したがって、物件価格5,000万円でのローンは十分に現実的です。この戦略により、金融資産6,500万円のうち約6,200万円を手元に残し、
そのうち約3,100万円(リバランス後)を長生きリスクに備えた投資に充てることができます。
🗣️ 相談者
投資資産を減らさなくて済むのは嬉しいですが、
私の高いリターンを狙う投資規律が崩れたらどうしますか?
株価が下がったら、大きな損失になりますよね?
【リスクヘッジの規律】
💬 MK
50歳からの投資において、株価下落は最大の脅威です。
このリスクは、確実な収入とローンの規律でヘッジします。ローンの返済原資は、期待リターン15.27%・リスク17.27%の株式投資ではなく、
あなたの確実な労働収入と退職金で賄われます。つまり、ローン返済と投資ポートフォリオは完全に切り離されています。
株価暴落が起きても、「ローン返済のために株を売る」という最悪の事態は回避できます。
【教訓 II】ローンの安全性は投資の成績に依存させない
ローンを「確実な返済原資(給与+退職金)」で完結させること。
それこそが、投資家にとっての最大のリスクヘッジです。
🗣️ 相談者
それは安心です。
ですが、もし10年間株価が低迷し続けた場合、ローンの返済はできても、
安値で株を買い増しできないどころか、株を売って繰上返済する必要が出てくるかもしれないんですよね?
💬 MK
その通りです。その状況こそ、規律の真の試練です。
株価が低迷し、定年時の負債解消が危うくなる場合、
優先すべきは「運用を続ける規律」ではなく、
生活基盤を守る規律です。たとえ株を売ってローンを繰上返済しても、
それは「不確実なリターン」より「確実なコスト削減」を選んだ合理的行動です。
50代以降の資産戦略では、収益より安定を優先する判断が長期的成功を支えます。
【教訓 III】生活の安定は収益性の追求に勝る
投資の“勝ち”とは、
価格変動に一喜一憂することではなく、
生活の安定を最後まで維持することです。
ローン解消という「安定の規律」を優先する行動こそ、
最終的に投資家としても最も理にかなっています。
🗣️ 相談者
納得しました。
つまり、毎月(または毎年)のローン返済額が、
私の労働収入で完全に賄いきれることが、このフルローンに近い戦略の絶対的な前提条件なのですね。
たとえば、今の家賃が年間144万円、貯金が年間150万円できているなら、
144+150=294万円/年 × 15年 = 約4,410万円。
この範囲内であれば、現実的に返済できそうだと考えればいいですね。
💬 MK
まさにその通りです。
ローンの上限は、確実なキャッシュフローで返済できる額です。つまり、「今の生活を維持しながら返済できる額」こそが、無理のない合理的な上限です。
高い収益性は、強固な規律とリスクヘッジの上にしか成り立ちません。
まとめ(シリーズ完結)
住宅購入・投資・ローン返済――
どれも「規律」を失えば、たちまちリスクの連鎖が起こります。
- リバランスの規律(第1回)
- 目的別資金管理の規律(第2回)
- 生活基盤を守る規律(第3回)
3つの規律は、単なる投資ルールではなく、人生の経済設計を貫く思考法です。
感情に流されず、数字と規律で生きる。
それが、長期投資家として求められる姿勢です。
💬 MK(税理士の視点から)
住宅ローンを検討する際、「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」を過度に意識しすぎる方が少なくありません。
控除はあくまで“おまけ”であり、これを目的にローンを組むのは本末転倒です。ただし、取れるメリットは確実に取ることも、冷静な資金設計の一部です。
近年は控除の適用年数が短くなっており、たとえば今回のように「15年で借りて実質10年で返済」する設定は、
現行制度(中古住宅で10年間の控除)との整合も取れています。なお、現行の住宅ローン控除制度は2025年末までが期限となっています。
今後の税制改正で内容が変わる可能性があるため、適用を検討する際は最新の制度を確認することが大切です。
当ブログでも今後、税制改正の動向には随時触れていきます。