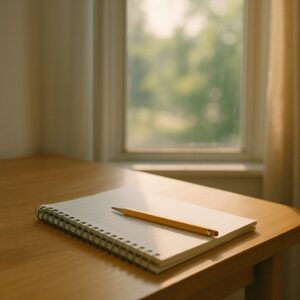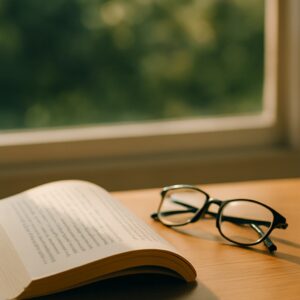【中学受験、父と息子の365日戦記】第5話|国語の壁と、自分の未熟さに気づく
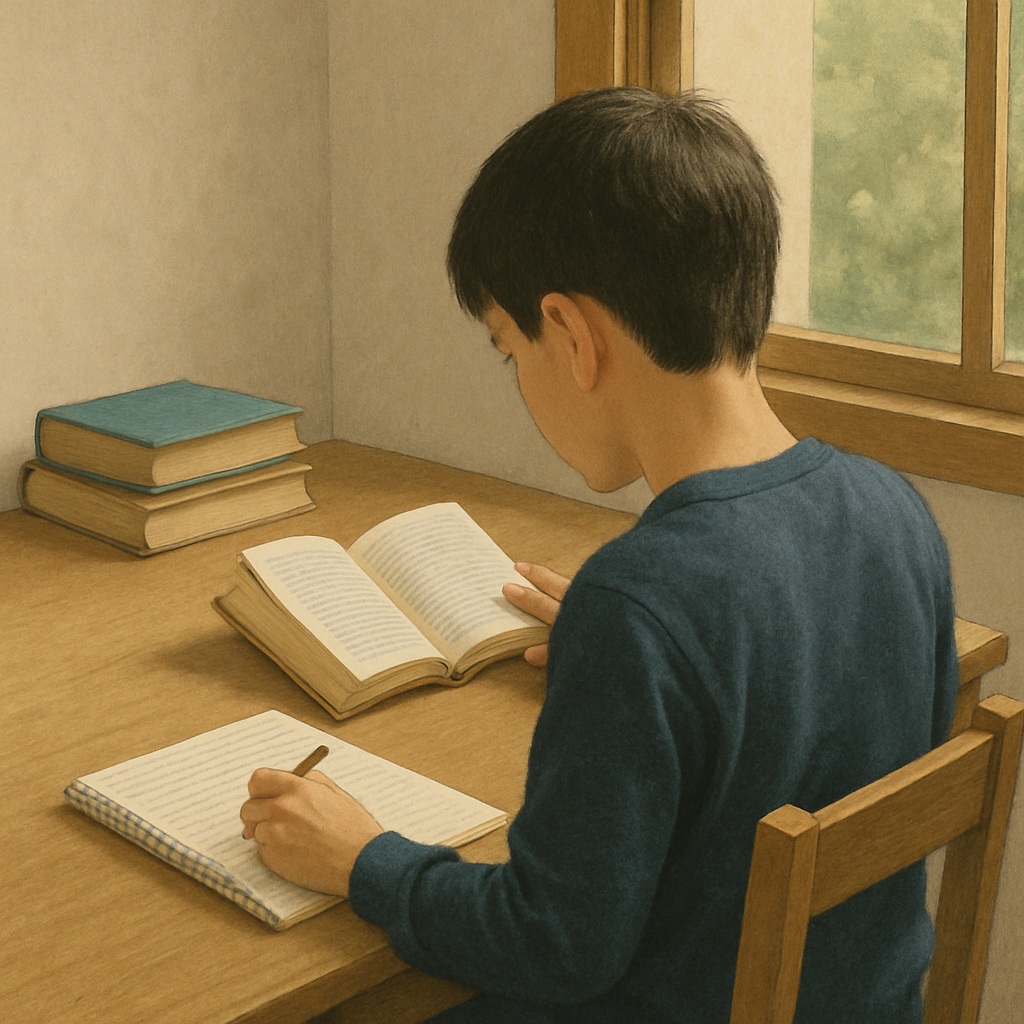
春期講座が終わり、気がつけば4月も後半。
入塾して2か月が経とうとしていた頃、私は「国語」の壁に直面していた。
正確には、“息子が”ではなく、“私が”――だ。
息子の国語の成績は、なかなか安定しない。
記述問題は空欄だったり、ピントがずれていたり。
復習テストや月例テストでも、平均点に届かないことが続いた。
「もっとちゃんと読みなさい」
「設問の意図を考えなさい」
何度、そんな言葉を飲み込んだだろう。
実は私は、息子の国語テストを毎回解いている。
本文を読み、設問に答え、解説を読む。
最近では、少し楽しくなってきている自分がいる。
登場人物の心情。
時代背景と描写のギャップ。
大人になってから読む文章が、こんなに面白いなんて思ってもみなかった。
でも、息子にはそれが難しい。
背景や心の機微を読み取るには、人生経験が足りない。
だから「ズレる」し、「分からない」となる。
それを、私はどこかで「努力不足」と決めつけていた。
実力ではなく“意識の問題”だと思い込んでいた。
…傲慢だった。
あるとき、記述問題を一緒に見返していて、息子が言った。
「これって、何が正解なの?」
私は答えに詰まった。
解説には“模範解答”が書いてあるけれど、そこに至る“思考の道筋”をうまく説明できなかったのだ。
そのとき気づいた。
私自身、国語を「理解したつもり」で読んでいただけだったのだ、と。
中学受験の国語は、奥が深い。
そしてそれは、子どもだけでなく、大人の読解力や人間力まで試してくる。
私がすべきだったのは、「読め!」と叱ることではなく、
一緒に感じて、一緒に迷って、一緒に育つことだった。
そう思えた日から、私は少しずつ“父親”として成長している気がする。
少なくとも、自分の未熟さに気づけるようにはなった。
(続く)
---
※この物語は随時更新しています。次話はこちら → 第6話