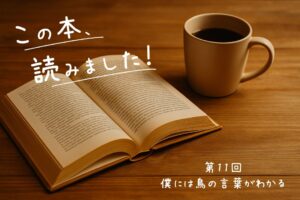【中学受験、父と息子の365日戦記】第16話|10月度後編 試練のとき

小学校最後の運動会。
徒競走では初めて1位を取り、組体操も堂々とこなしていた。
あの誇らしげな表情は、きっとこの先も忘れない。
ところが、その夜。
息子は夜中にリビングのパソコンを開いていた。
前の週も、テストのプレッシャーを理由に同じことをしていた。
「ストレスが溜まるのも分かるけど、夜中に遊ぶのは違う」――そう思いつつ、
もう以前のように怒鳴ることはできなかった。
ゲームもYouTubeも制限されている中で、すべてを我慢させるのは酷なのかもしれない。
それに、息子も「これが良くないこと」だと分かっている。
その“分かっていながらやってしまう”感覚は、親である私にも心当たりがあった。
頭では理解している。
短い時間の積み重ねが、合否を分けることもある。
この小さな油断の積み重ねが、人生の舵を握る力になるかもしれない。
けれど、今の段階で「そんなことをしていると不合格になるぞ」と脅すのも違う気がした。
まだ不合格になったわけでもないのに、
未来の結果で子どもを縛るのは、あまりに大人の都合だ。
結局、親に求められているのは、
「子どもをそのまま受け入れ、結果も受け入れ、それでも信じること」なのだろう。
中学受験の専門家・長谷川智也先生の言葉を借りれば、
「子を塾に入れ、お金を出した時点で、親としての役割は果たしている。
その後は、子の意欲と成長を見守るだけでいい」。
その言葉が頭をよぎる。
それでも、理屈では分かっていても、感情はついてこない。
私は息子の教材を管理している。
どこが未完了で、どの単元が抜けているのかが、手に取るように分かる。
「やるべきことをやっていない」現実を目の前にすると、
どうしても一言、言いたくなってしまう。
日曜特訓のテストは散々。
レギュラーの復習テストは粘って上位に入っているが、
10月26日の合否判定テストの結果は明らかに落ちていた。
苦手の社会が平均点を下回り、国語と算数が伸び悩んだ。
「苦手科目を得意科目でカバーする」という前提が崩れ、
4科目での総合偏差値は久しぶりに55を下回った。
本人はまだ結果を見ていない。
きっと、見た瞬間に落ち込むだろう。
だが、私は妙に冷静だった。
「夏以降、勉強時間が減ったのだから、こうなるのは当然だ」
「塾のテストは本当によくできている」――皮肉を込めて、そう思った。
おそらくこの結果が、息子の気持ちを少しは変えるだろう。
もしこれで危機感を覚えるなら、それでいい。
私が焦るより、息子が感じることのほうがよほど意味がある。
その一方で、心のどこかでこうも思っていた。
「勉強が足りないことは分かっている。
でも、塾が楽しくて、友達と笑い合っている。
その時点で、もう十分じゃないか」
10月下旬、お風呂での会話。
息子がぽつりと言った。
「塾の勉強って、楽しいね。もっと早くから通っておけばよかった」
「その割にはあんまりやらないね」と言いかけたが、飲み込んだ。
彼は続けた。
「9月に戻れるなら、もっと真面目に国語の基礎やって、計算ドリルも毎日やって、特訓の宿題もある程度やるのに」
私は思わず笑った。
「10月にそう思えるのは、むしろ早くていいよ。
これが試験1か月前だったら、後悔だけで固まって動けなくなってたよ」
息子は驚いた顔をした。
きっと「今頃後悔しても遅いぞ」と言われると思っていたのだろう。
その表情に、ほんの少しだけ救われた気がした。
だが、行動は変わらない(笑)。
宿題は最小限。計算ドリルは10日分溜まり、机には中途半端なノート。
頭では分かっているのに、行動が追いつかない――それは息子も私も同じだ。
私は現実を理解している。
このままでは第1志望校は厳しい。
けれど、第2志望、第3志望であれば合格の可能性は十分にある。
そして、それでいいとさえ思っている。
ただ、息子は違う。
彼の目標はあくまで第1志望校。
ならば、その覚悟にふさわしい努力をすればいい。
私が無理やり本気にさせることではない。
「第1志望を目指しているのは息子であって、私ではない」
そう思い直した。
夜、机の上に置かれた息子の答案を見ながら、
私はようやく気づいた。
――この「わかっているのに動けない」という感覚こそが、
今、私たち親子に課された試練なのだと。
子どもは現実から目をそらし、
親は感情に負けて理性を保てない。
どちらも未熟で、どちらも成長の途中。
試練とは、子を試すものではなく、
親をも試すものなのかもしれない。
(続く)
※この物語は随時更新しています。次話はこちら → 第17話
---